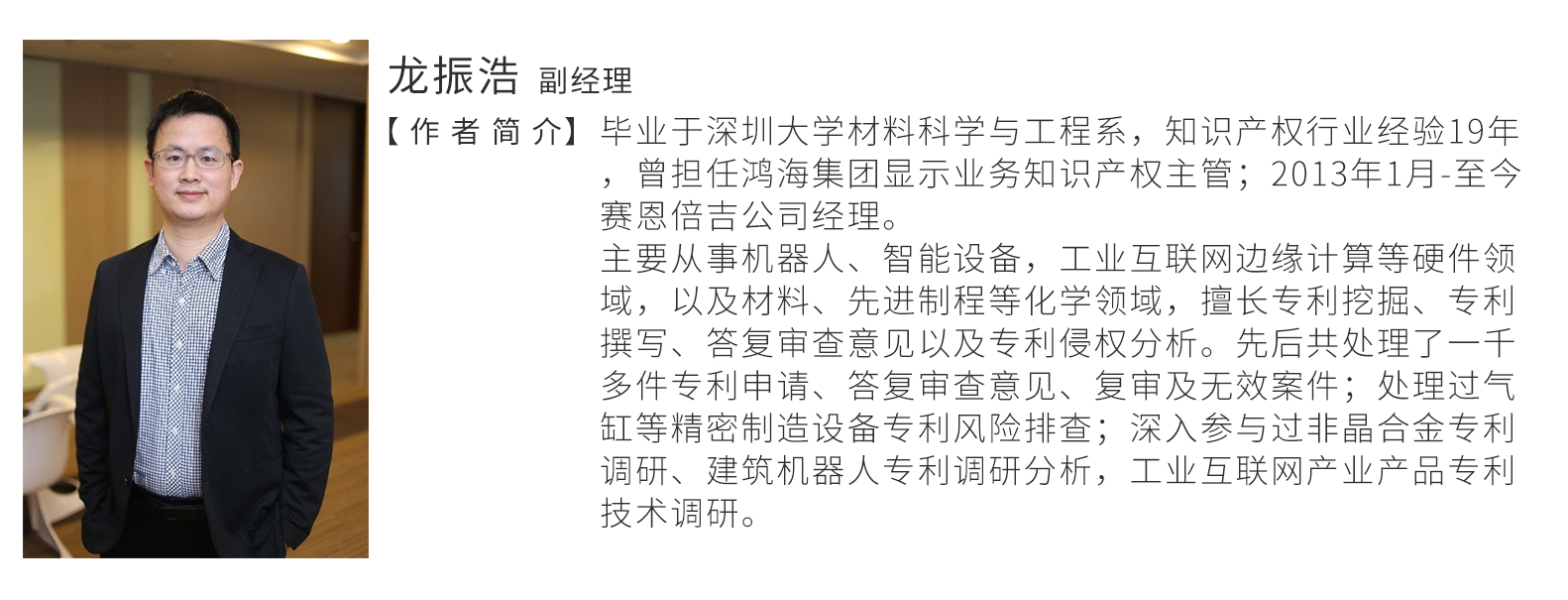著者:龍振浩時間:10.06.2020
2008年6月5日、国務院は「国家知的財産権戦略要綱」を公布し、知的財産権が国家戦略に上昇したことを示した。政策の推進に伴い、社会革新の活力も刺激され、企業革新の主体的地位もより明確になった。科学技術型企業も研究開発革新と知的財産権保護の重要性をますます認識している。
大・中型科学技術企業にとって、知的財産権保護の実行は通常、知的財産権管理部門の設立を通じて行われる。研究開発と保護のシステムを構築するには、知的財産権の専門家と研究開発者の良好な相互作用、協力が必要である。中小企業に対しては、知的財産権の保護は多くが外部代理の方式を採用しており、研究開発者は技術的な説明だけを提供しており、研究開発者は知的財産権、特に特許という専門性の強い知識に欠けている。研究開発者(発明者)は革新的な技術案に貢献する鍵となる側として、特許知識の常識を知っていれば、知的財産権保護に大いに役立つ。筆者は長期にわたって各種類の発明者に接触し、発明者に接触する過程でも多くの発明者が提案した共通性のよくある問題を発見し、特に整理して、研究開発者の特許に関する疑問に対して解答する基本常識にまとめた。
[質問1]:出願を提出すれば、特許権があるのではないでしょうか?
特許出願は審査認可制度であり、出願を提出すれば必ずしも許可されるとは限らない。特許出願の種類には、発明、実用新案及び意匠が含まれる。発明特許が公開された後、出願人の実質審査を経て、授権条件に合致した場合、発明特許権を付与する。授権するかどうかは、実体審査の結果に基づいて決定する必要がある。
[質問2]:独自に開発した製品や技術などは、特許出願は大丈夫でしょうか?
研究開発者は自主革新であれば、自主知的財産権があると考えている。実はそうではなく、特許は独占権であり、自主開発の技術成果は特許を申請しなければ、法律の確認と保護を得ることができない。我が国では、特許出願は先願原則を採用している。そのため、研究開発者が適時に申請せず、他人に先を越され特許権を付与された場合、研究開発者は他人の法的責任を追及することができない。
[質問3]:現時点ではアイデアしかありませんが、申請できますか?
一部の研究開発者は技術案がまだ生産に投入されておらず、製品が登場していないと感じているが、この時特許を申請するのは時期尚早で、製品が大規模に生産に投入されてから特許を申請するのが適切だ。特許出願の基礎はすでに市場に存在する製品ではなく、必ずしも成形された製品ではない。自然法則の利用+技術問題の解決+技術案のある+工業的に利用可能な条件を満たせば、特許出願に着手することができるという確実で実行可能な考え方があれば。
[質問4]:製品は出荷されていますが、特許を申請することはできますか?
発明者は生産任務を急いで、後で出荷したことに気づいて特許保護を申請することを思い出したが、実際には、これは比較的適切ではなく、幸いにも特許を取得しても、特許の新規性が破壊されている可能性があるため、特許は不安定な状態にある。この時、誰かが権利侵害を発見して訴訟を起こした場合、権利侵害者は特許出願の日に技術が公開されていることを理由に抗弁する可能性が高く、抗弁が成功すれば、それまでに費やした精力、時間、お金はすべて水の泡になる。特許出願はできるだけ早くしなければならない。
[質問5]:特許出願しましたが、授権できるのはいつですか?
実用新案特許の審査・認可が速く、できるだけ早く相応の保護を得ることができ、通常1年程度の時間を必要とする。発明特許は通常2〜5年の審査承認期間を必要とする。国家の知的財産権の程度の向上に伴い、特許審査の承認時間も相対的に短縮された。ここ2年間の審査状況を見ると、実用新案特許は通常9カ月程度でライセンスできる。発明特許は通常2年半〜4年程度かかる。意匠特許は通常6ヶ月程度である。
[質問6]:ライセンスさえすれば、私の製品や技術を保護することができますか?
必ずしも、特許権保護範囲とは、特許権の効力に及ぶ発明創造の技術的特徴と技術的幅を指す。したがって、特許権の範囲は特許権の保護範囲である。特許が付与されているが、特許保護範囲が製品や技術を保護できない場合もある。そのため、特許権の比較的合理的な範囲の獲得は製品設計レベルまたは技術レベルの影響を受けるほか、特許権範囲の執筆に対する特許代理士の掌握度の影響を受け、品質のある代理店を選択することが重要である。また特許権は排他的実施権であり、発明者の製品は依然として他人の基礎特許の範囲に入る可能性があり、または依然として権利侵害のリスクがある。
[問題7]:発明の核心技術は他の人のもので、改良特許を申請することができますか?
はい、既存の特許に基づいて改善を行い、新しい技術効果を取得すれば、新しい特許を出願することができます。もしあなたが元の特許に存在する問題を発見したら、改良して、新しい特許技術を形成することができて、特許を申請することができて、これは改良型発明に属して、比較的によく見られる発明創造タイプです。
[質問8]:1つの製品やプロジェクトを複数申請することはできますか。発明の改良だけを再申請する必要はありますか?
1つの製品やプロジェクトの研究開発プロセスは、複数の技術改良や革新に関連しており、強固な特許ポートフォリオや特許パッケージの形成を図るために、革新点を分析するための掘削レイアウトを行うことができる。一部の発明者は、特許を出願した後、特許を再配置する必要はなく、反復製品を開発したり、新たに改良したりしても、特許を出願しないと考えている。このようなやり方の結果は、他の人がこの製品を改良して特許を申請した場合、逆に元特許権者の製品の更新を制限することになるので、元特許権者はうっかりして権利侵害者になってしまう。
[問題9]:1つの技術成果は1種類の特許しか出願できないのか?
必ずしもそうではないが、一部の発明者は、1つの技術成果は1回に1種類の特許しか出願できない、すなわち発明特許しか出願できない、または実用新案特許しか出願できない、または意匠特許しか出願できないと考えている。1つの製品発明は同時に多種の特許を出願することができ、技術方案も同時に実用新案と発明特許を出願することができる。いくつかの重要な製品発明に対して、発明者が発明特許だけを出願し、その時他の人が「二重管理下」で、同時に発明特許と実用新案特許を出願すると、彼はまず実用新案特許を取得し、製品の特許権を持つことになる。発明者がこの製品を使用すると、かえって権利侵害になる。
[質問10]:製品は中国でのみ特許出願されているが、製品は他国、例えば米国に販売され、保護されるだろうか?
保護を受けることができず、特許は地域性があり、特許は出願国または地域でのみ有効である。だから1つの製品は多くの国に販売され、その特許出願も多くの配置を考慮する必要がある。
[問題11]:製品はすでに特許を出願しているが、特許侵害問題を確認する必要があるか?
特許権は排他的実施権とも呼ばれ、すなわち、他人は特許権者の許可を得ずに実施してはならない。そのため、製品が特許出願済みであっても、他人の基礎特許の範囲に入ることを排除せずに権利侵害となるため、製品を販売する前に特許リスク評価を行う必要がある。特許は自分用だけではなく、他人用を制限するために使われているので、競争相手の製品をめぐって事前に相応の特許を配置し、それから特許を通じて競争相手を制限し、打撃し、時には競争相手に対して他の伝統的な競争手段にはない打撃と制約効果を達成することができます。
【問題12】:特許出願は技術成果を保護する唯一の方法であるか?
技術成果の保護には2つの方法を採用することができます:特許出願は法律によって保護され、商業技術の秘密を通じて技術所有者自身が保護され、両者にはそれぞれメリットとデメリットがあります。技術成果が特許を出願した場合、他人が権利を侵害した場合、法律の強制的制裁を通じて権利侵害者を制裁して特許権者の利益を保護することができる。不利な点は、この分野の一般技術者が公開された技術案を通じて実施できるように十分に開示しなければならないことであり、これは他の人にこの技術案に基づいてさらに研究開発の機会を提供することができる。技術成果が商業技術秘密を用いて保護されれば、特許出願のように技術案を公開する必要はなく、保護措置が適切であれば、他の人には理解されにくい。
[質問13]:特許証明書があれば、特許権は有効ですか?
必ずしもそうではないが、特許権期限とは特許権の法が定期的に終了する時間を指す。特許権の授権公告の日から、他の事由により特許権が終了しなかった場合、当該特許権は特許権の期限が満了した日まで終了する。特許法の規定によると、発明特許の期限は20年である。実用新案特許と意匠特許の期間は10年であり、いずれも出願日から計算される。特許が期限切れになると、特許権は終了する。現在、未払いによる特許権の早期終了も一般的で、Patentcloudプラットフォーム(https://app.patentcloud.com/index.html)で特許を検索することで、特許権の最新の法的状態を迅速に知ることができます。たとえば、次の図に示します:

以上の特許常識は研究開発者の特許保護意識の向上に積極的であるが、企業や研究開発者がコア特許を構築して経済のモデルチェンジや新興産業の発展を助けようとするにはまだ十分ではなく、企業や研究開発者は知的財産権専門職の協力を借りて推進する必要がある。