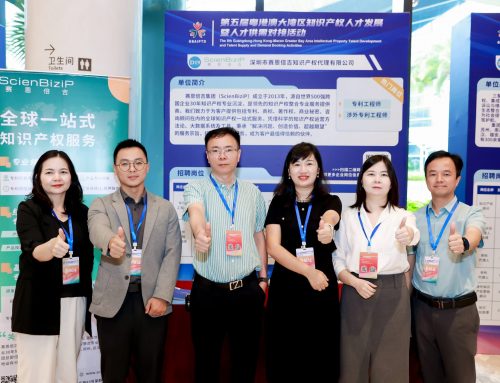12月6日、「中国知的財産権報」第2544期第08版の「理論的視点」欄には、サイオン倍吉創始者兼CEOの謝志為氏、サイオン倍吉賦能研究院院長の薛暁偉氏の署名記事「市場に立脚して高価値特許を育成する」が掲載され、全文を以下の通り転載した。
本文の著者
謝志氏はサイン・ベージ創業者兼CEO
薛暁偉賽恩倍吉賦能研究院院長
知的財産権の理念がますます深くなるにつれて、革新主体の特許品質、特許価値に対する重視度は日増しに向上し、特に高価値特許の育成活動は、革新主体の知的財産権活動の主要な方向となっている。各種類の革新主体はすでに、高価値特許を育成し、真に経済効果をもたらすことができ、あるいは競争優位を確立することができ、特許制度の「天才の火に利益の油を注ぐ」べき意義にもいっそう合致していることを認識している。筆者から見れば、革新主体は高価値特許の育成活動を展開し、一方で、高価値特許の育成の概念を明確にし、どの特許が高価値特許に属するかを明確にしなければならない。一方、高価値特許育成の鍵を明確にし、重要な一環として高価値特許育成の成功を確保しなければならない。
評価基準を明確にする
現在、業界で認められている高価値特許評価基準は、法的価値、技術的価値、市場価値の3つの次元から着手されている。その中で、法律の価値は権利の安定性、権利侵害の判定可能性などを含む、技術的価値には、技術的成熟度、技術的代替性などが含まれる。市場価値には、市場の現在の応用度、将来の応用市場規模などが含まれる。さらに言えば、多くの地方が打ち出している高価値特許育成地方基準は、その上で最適化・改正されたものである。
筆者から見れば、上述の高価値特許の評価基準は、より多くは結果から出発して、どのような特許が高価値特許の範囲に組み入れることができるかを反映して、高価値特許概念の外延を体現している。同時に、評価次元が多く、高価値特許概念の核心をつかむことは難しい。
実際、高価値特許の重点は「高価値」にあり、特許の価値は技術と市場を繋ぐことにある。そのため、高価値特許概念の内包は、特許の背後に代表される技術の市場または産業における価値実現の程度、および特許の背後に代表される技術が関連する市場参加主体によって現在および将来採用される程度に重点を置くべきである。1件の特許に代表される技術が、市場関連の参加主体に広く採用され、産業や企業において大きな価値を生み出している場合、その特許は高価値特許の範疇に属すべきである。
このような評価基準は、より価値の高い特許の役割を果たすことができる。企業レベルでは、高価値特許は市場の将来性のある技術を狙っており、特許の革新性を利用して、企業製品がより優れた性能で市場競争に勝ち、さらに競争優位を形成している。社会面では、各種類の革新主体は高価値特許を育成し、さらに競争優位を形成するために、絶えず新技術を研究開発し、新分野を開拓し、新業態を形成し、相互の良性競争があってこそ、全体の技術レベルの革新発展を推進することができる。
育成経路の探索
筆者は、高価値特許の育成経路について、高品質創造、高品質出願、高基準授権、正確な長期配置、正確な政策支援、高レベル選別と評価などの方面から着手することができるだけでなく、特許配置の現状分析、配置済み特許の組み合わせの最適化、配置されていない方向の発掘と育成、特許価値評価の授権、特許運用の育成の強化などの方面で力を発揮することができると考えている。
具体的に企業の高価値特許の育成については、まず特許の企業に対する根本的な効用は、その法律上の排他性を利用して、競争相手の特許製品の生産、使用、販売、輸入を制限することができることにあることを認識しなければならない。そのため、高価値特許の育成の鍵は、特許の排他的制限競争相手をうまく利用することができ、育成された特許が将来広く採用される可能性のある技術や製品に着目することができ、競争相手の技術や製品を特許権保護の範囲内に落とすことができ、それによって競争相手の市場占有率を減少させることができ、あるいはこの広く採用された技術や製品からライセンス料を受け取ってそのコストを高くし、企業の市場における相対的な競争優位を形成することができるかどうかにある。通信分野の標準に必要な特許の権利者は、通信業の経営主体が相互接続の需要に基づいて必ず通信標準技術を採用し、さらに関連市場の参加主体に授権許可料を受け取ることができることを認識し、ビジネスモデルを形成し、関連標準に必要な特許も高価値特許となった。他の産業がすべての関連市場主体に標準を利用してカバーすることが困難な場合、革新主体の高価値特許育成は依然として関連市場の参加主体を狙い、将来広く採用される技術や製品をカバーすることを堅持しなければならず、カバー面が大きいほど、特許は大きな価値を生むことができる。
産業次元へのフォーカス
実際には、一部の企業の特許レイアウトの目は自分の技術に限られ、その中から高価値特許を発掘し、選別する傾向があり、これにより企業の特許レイアウトは自分の技術や製品を保護することができるだけで、産業チェーンの角度から、広範な市場の次元に向かって配置することができず、競争優位を形成することができる。
筆者は、革新主体は自身の特許価値を高め、競争優位を形成しなければならないと考え、一方で、産業技術の研究開発と市場状況の調査研究に精進し、関連参加者の現在の製品、技術、市場などの情報と未来の発展傾向を理解し、高価値特許の育成とその未来の価値実現のために、堅固な情報基礎を打ち立てなければならない。一方、上述の産業、技術、市場調査に基づいて特許レイアウトを整備し、特許ごとに権利項シミュレーションを行い、特許を育成の初め、すなわち価値向上のために準備を整え、さらに特許価値の実現のために保障を提供する。
同時に、革新主体は産業、技術及び市場状況を結合し、特許ポートフォリオを育成しなければならない。製品や技術的に補完的な特許ポートフォリオ、代替的な特許ポートフォリオのように、科学的で合理的な特許ポートフォリオは、高価値特許の適用シーンをさらに拡大し、その価値度を高めることができる。また、革新主体は特許のライフサイクル管理の異なる段階で、関連する市場参加者の動態を適時に更新し、各国の特許制度を活用し、リアルタイム、動態調整、特許範囲の修正または補強、同族特許または特許家族の増加などに依拠し、育成した高価値特許を技術の革新と市場の変化に伴い脈動させ、特許に本当に生命力を持たせる必要がある。